成年後見/任意後見
~成年後見制度とは?~
自分の行為が、どういった結果をもたらすのか。
私たちは強く意識せずとも、日常的に様々な判断をしながら生活をしています。
しかし判断能力が不十分な場合、不利益を被ってしまう可能性があります。
そういったことを防ぐため、判断能力の不十分な方(認知症など)をサポートするのが、成年後見制度です。
こんなケースで有効です
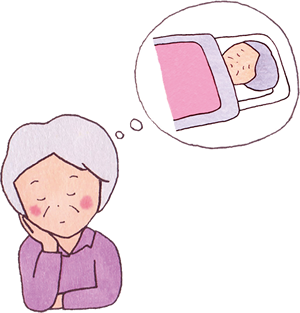
- 今は元気だけれど、将来認知症になって判断能力が低下した場合に備えたい
- 知的障害のある子供がいて、自分が亡くなった時が心配
- 一人暮らしの親がいるが、自分が遠方でサポートできない
- 親と同居している親族が、親の貯金を使い込んでいる
- 相続が発生したが、相続人が認知症で協議ができない
- 強引に頼まれると、不必要なものまで買ってしまう
- 施設に入所中の方へ、借金の督促が届いたが返済できない
どのような支援をするのか?

サポートが必要なご本人の状況等に応じて、財産の調査・管理と身上監護を行います。
財産管理は、日常生活に必要な出費や、年金等支払い手続き・受領、遺産相続の手続きや不動産管理・処分まで多岐にわたります。
身上監護とは、実際に同居をしたり介護をしたりということではなく、治療や療養・介護などに関する契約や手続きを行うことです。
~ 後見制度の種類 ~
後見制度は、大きく分けて2種類あります。
1.法定後見制度
すでに判断能力が不十分な方をサポートするための制度で、家庭裁判所に申立てをし、支援者を選任してもらいます。
医師による診断書を踏まえ、どのようなサポートが必要か、裁判所が判断します。
裁判所に選任された支援者は、ご本人の代わりに法律行為を行う「代理権」や、行為について「同意権」「取消権」を付与され、支援にあたります。
支援者は、家庭裁判所に財産目録や収支報告を提出し、ご本人の状況を報告する義務があります。
|
補 助 |
支援する人は「補助人」と呼ばれます。 日常生活に問題はなく、重要な契約などの判断はできるものの、少し不安がある・・・といった方をサポートするための制度です。 申立時に、本人が指定した特定の法律行為の代理権や、同意権・取消権によって支援します。 ※ただし、補助人に認められている同意権・取消権の対象は、民法第13上第1項に定められているものに限られています。詳しくはご相談下さい。 |
| 保 佐 |
支援する人は「保佐人」と呼ばれます。 日常生活に支障はないが、重要な判断はできない・・・という方をサポートします。 財産管理はご本人が行うことができます。 補助同様、申立時に本人が指定した特定の法律行為の代理権や、同意権・取消権によって支援します。補助と違うのは、同意権・取消権の対象が限定されていない点です。 |
| 後 見 |
支援する人は「後見人」と呼ばれます。 日常生活を一人で行えない方が対象です。 ご本人に代わって全ての法律行為を代理して支援します。 |
2.任意後見制度
将来の不安に備えて利用できる制度です。
今は元気で問題はないけれど、認知症になってしまったらどうしよう・・・といった場合に、あらかじめ信頼できる人(親族・知人・司法書士や弁護士など)と任意後見契約を結んでおきます。
任意後見契約は公正証書で作成します。
実際に支援が必要な状態になったら、裁判所に申立てをして「任意後見監督人」を選任することで、はじめて効力を発します。
監督人が後見人の職務をチェックするので、悪用される心配もなく、自分で後見人を選べることが、最大のメリットです。
遺言書の作成、死後事務委任契約*などと合わせて検討されることが多いです。
※死後事務委任契約とは、委任者(本人)が第三者(個人・法人を含む。) に対し、亡くなった後の諸手続、葬儀、納骨、埋葬に関する事務等についての代理権を付与して、死後事務を委任する契約をいいます。
参考ブログ:死後事務委任と遺言で死後の安心を

成年後見制度は非常に有効な制度ですが、申立てまでが大変です。
弊所では、法定後見の申立や任意後見契約のお手伝いをしております。
それぞれのケースにあった安心感のある支援方法をご提案しますので、お気軽にご相談下さい。
参考ブログテーマ:成年後見制度
